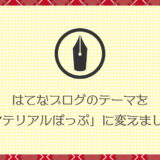スポンサーリンク
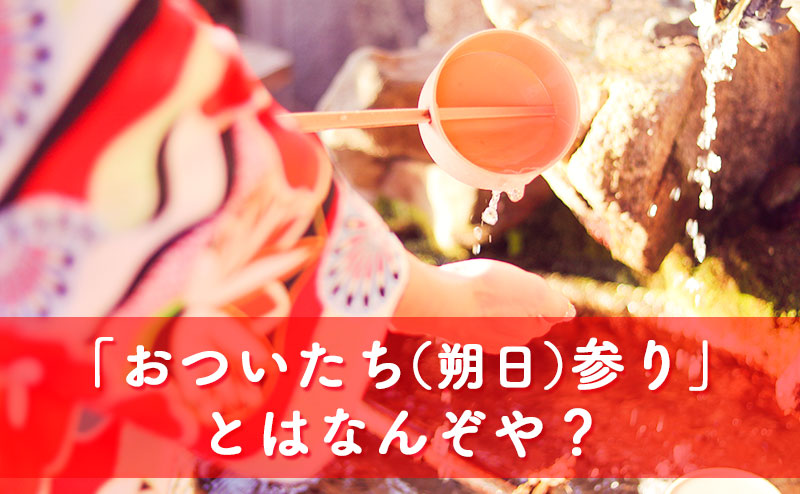
かなり今更ですが、去年、2017年の12月1日に「お伊勢さん」に「おついたち参り」に行ってきました。
その辺のことも早くブログに書こうと思っていたのですが、そもそも「おついたち参り」って何となく知ってるけど、なんとなくわからないな、まず説明できないなと思ったのでほとほと今さらですが「おついたち参り」について調べてみた。
 【伊勢詣で】せっかくお伊勢さんに行くならここだけは巡っておきたい個人的おすすめ参拝ルートまとめ
【伊勢詣で】せっかくお伊勢さんに行くならここだけは巡っておきたい個人的おすすめ参拝ルートまとめ
これはもう読んで字のごとく、
毎月1日に、つまり月の最初に神社に参拝することです。
以上。
って、いやいやそれで終わるとあっさりしすぎなのでもちょっと掘り下げます。
「おついたち参り」は、正月の元旦をはじめとして毎月初めの1日に神社に参拝し、神恩感謝の気持ちと新しい月の無病息災などを祈念する古くから伝わる風習です
なのでお正月の元日に神社へお参りするのも当然「おついたち参り」になるわけですね。
「おついたち参り」では、
- 前月の感謝を捧げる
- 新しい月の無病息災や家内安全、商売繁盛などを祈念する
- 神様に誓いを立て、自分自身を新たにする
といったような事を参拝します
あと神社によっては「おついたち参り」限定の御朱印があったりもするので、御朱印をいただくのもいいですね
「おついたち参り」がいつから始まったかの起源はちょっとわからなかったのですが、どうやら江戸時代にはこの風習が定着していたみたいです。
そもそもどうして1日(ついたち)にお参りする風習が生まれたのかというと、旧暦の太陰暦だとちょうど、
- 1日が新月
- 15日が満月
になるのです。
ちょうど区切りもいいので、もしかしたら1日と15日に神社へお参りしようとなったのかな。
「ついたち」という呼び方は、月の満ち欠けからきていて、月の始まりの「月立つ」が転じて「ついたち」になったらしい。
奈良から平安時代には1日のことを「ひとひ」とも呼んでいたそうですが、「ひとひ」という言葉には、「1日」の他にも「ある日」、とか「24時間」といった意味も含まれていたみたいで、ややこしいので「1日」は「ついたち」と読むようになっていったらしいです。
「おついたち参り」と書いてますが、「1日」にお参りすることを「おついたち参り」といっているので、「朔日参り」という風に書かれることもあります。
「朔日」は「1日」のことですからね。
「朔日」は「さくじつ」って読むのが一般的かなと思いますが、訓読みだと「ついたち」という読み方になるのです。
ちなみに「朔」の字1文字だけでも「ついたち」と読めるんです。
勉強になりますね、役にたつかどうかは置いといて。
あとは「おついたち参り」と「お」を付けていう事が多いけど、たんに「ついたち参り」という事もあります。
今でも多くの神社では毎月1日と15日に「月次祭(つきなみさい)」という神事が行われています。
「つきなみ」とは月毎に国や地域の安泰と、氏子や崇敬者の平安・幸福を祈るお祭りです。
毎月はじめの「月立ち」の新月に神社で神事が行われていたから、1日に神社へお参りするというのが習慣化していったんでしょうね。
それにしても1日は「おついたち参り」という言葉が定着していったのに、15日は特に「15日参り」という言葉は聞かないですねぇ。
「月参り」という言葉は聞きますが。
ぶっちゃけどこの神社でもいいと思います。
まぁでも「月次祭(つきなみさい)」では氏子の平安・幸福もお祈りするので、自分の住んでいる地域の氏神様の神社に行くのもいいですね。
なによりもし毎月「おついたち参り」へ行くのであれば、やはり近くの神社の方がいいかなとも
あと「一の宮」といわれる地域の大きな神社とか、せっかくだし気合い入れて
「お伊勢さんに行くぞー!」
とか遠方にお出かけするのもありでしょう。
楽しいし。
神社に参拝に行くという気持ちがまず大事なんでしょう。
 【伊勢詣で】せっかくお伊勢さんに行くならここだけは巡っておきたい個人的おすすめ参拝ルートまとめ
【伊勢詣で】せっかくお伊勢さんに行くならここだけは巡っておきたい個人的おすすめ参拝ルートまとめ
「おついたち参り」で人が賑わうことから、どうやら昔から1日には神社の近くで市がたったり、朔日餅(ついたちもち)が売られたりとしていたそうです。
名古屋の熱田神宮では、境内に朔日市がたって「朔日餅」が販売されてるみたいです。
しかも毎月お持ちの種類が変わるんだそうです。
これは楽しみですね。毎月行きたくなるかも。ちょっと目的がすり替わってるような気もしますが(笑)
そして「伊勢神宮」と言えば老舗和菓子屋さんの「赤福」が有名ですね。
「赤福」ももちろん「朔日餅」がありますよ!
こちらも毎月お正月以外の1日に「朔日餅」が月替りで出ているのです。
あとお伊勢さん近くの「おかげ横丁」でも、毎月1日に朔日朝市がたったり、朔日粥が販売されたりもしてるようです。
石川県にある加賀一の宮の「白山比咩神社」、通称「しらやまさん」でも毎月「おついたち参り」の特別祈祷があるのです。
ちなみにしらやまさんの「おついたち参り」はなんと毎月1日の朝4時30分から!
約30分ごとにご祈祷・お神楽があります。
しらやまさんで「おついたち参り」の申し込みをすると、「おついたちまいりカード」なるものがいただけます。
そして「おついたち参り」の標として「月次御幣」というものが授与されるんだそうです。
毎月、月初めに「よし!今月(こそ)はこれをやるぞ!」と毎月目標を立てたりする事もあると思いますが、せっかくなら神社へ「おついたち参り」に出かけ、
「今月はこれを頑張ります!」
と目標を宣言するのもいいかもしれませんね。
お正月はやっぱり、1年の節目としてお参りに行くことが多いと思うけど、月ごとの節目として、わかりやすく1日にお参りするというのも毎月の振り返りにもなるかもしれないですね。
あ、神社ではあまり自分のお願い事ばかりをするよりも、感謝の気持ちとか目標を宣言する方がいいみたいですよ。
無事に過ごせたことへの感謝とか、新しい月の無病息災・家内安全・商売繁盛などを神様にお祈りしたりとか。
毎月、今月こそはこれをやるぞ!と思いながらまたできなかったりを繰り返しているので、「おついたち参り」で気持ちをリセットして頑張れる!かも。